




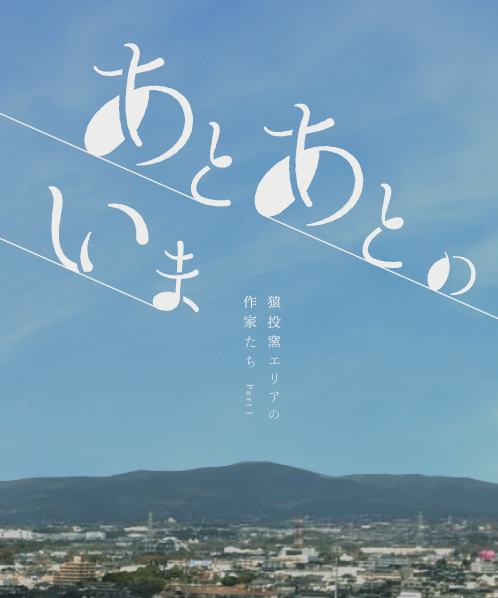
陶芸研究家の本多静雄が
調査・周知に貢献した猿投窯。
日本の三大古窯に数えられ、
現代の周辺窯業地の源流とも言える存在でした。
本企画では、その猿投窯エリアで
現代に活動する3名の陶芸作家を紹介します。

プロフィールを見る
| 2011 | 愛知教育大学大学院修了 |
公募展
| 2014 | 第10回国際陶磁器展美濃 |
| 2017 | 第3回金沢・世界工芸トリエンナーレ(金沢21世紀美術館/石川) |
主な展覧会
| 2011 | やきものの現在 土から成るかたちPartⅦ(ギャラリーヴォイス/岐阜) |
| 2016 | 進行形・女子陶芸II(茨城県陶芸美術館) |
手捻りで成形した棘を規則的に集積し、ゆっくりと染めるように着色します。
赤く染まった棘は熱い窯の中で蠢き、温度が下がるとピシッと静止します。
まるで生き物に流れる血が一瞬にして固まったようです。
“かつて生きていた”という緊張感の奥に私たちの永遠性を感じています。

プロフィールを見る
| 1987 | 沖縄県生まれ |
| 2012 | 沖縄県立芸術大学 工芸専攻 陶芸コース 卒業 |
| 2014 | 愛知県立芸術大学 大学院 陶磁領域 修了 |
| 2017 | 瀬戸染付工芸館 修了 |
公募展
| 2013 | 第44回東海伝統工芸展 入選(以後毎年入選) |
| 2015 | 第70回新匠工芸会展 入選 |
| 第6回菊池ビエンナーレ 現代陶芸の<今> 入選 | |
| 2018 | 第49回 東海伝統工芸展 中日賞 受賞 |
| 2019 | 第50回 東海伝統工芸展 愛知県知事賞 受賞 |
釉薬が厚く溜まったところに青みを増し、彫りの文様での濃淡に魅力を感じています。
またそのものの質感などから湿度や暖かみ、またその空気感を伝えられればと思っています。

プロフィールを見る
| 1983 | 神奈川県生まれ |
| 2011 | 女子美術大学大学院美術研究科 博士後期課程 修了 |
公募展
| 2005 | 朝日陶芸展 入選(-‘08) |
| 神戸ビエンナーレ現代陶芸コンペティション」入選(‘09) | |
| 2009 | 長三賞現代陶芸展 入選(‘11 審査員特別賞,‘15) |
| 2014 | 国際陶磁器展美濃 入選 |
| 2015 | 日本陶芸展 入選 |
主な展覧会
| 2008 | 個展(村松画廊/東京) |
| 2010 | 個展(コバヤシ画廊/東京)('12) |
| 2011 | 個展/銀座ギャラリー女子美(東京) |
| 飯嶋桃代 横田典子 二人展 (上野の森美術館ギャラリー/東京、女子美アートミュージアム/神奈川) |
|
| やきものの現在 土から成るかたちーPartⅦ (多治見市文化工房 ギャラリーヴォイス) |
|
| 2013 | 個展(メタルアートミュージアム光の谷 屋外展示/千葉) |
| 2016 | アジア現代陶芸展 (-‘19) |
土が揺らぐ。その揺らぎに寄り添うように生まれるかたち。
ツチ・ビト――土と人。人が土を用いて作るのではない。土の変化に任すのでもない。同じ立場で共に作る。それぞれがそれぞれとして繋がり、1つのかたちとなる。



−望月さんは今は長久手に住まわれて制作をされています。 まずは焼き物をはじめたきっかけからお伺いします。
私は子供の頃から手を動かすことが好きで、なんとなく美術系の大学に行きたいと思っていました。愛知教育大学の造形文化コースに入学し、ガラスや漆など他の工芸分野も体験した中で焼き物しかない、と思って3年次に専攻をしたのがきっかけです。そう思ったのは何故だったのか振り返ると、生の土を触るほどに知らない自分が出てくるような感覚の面白さと、焼いた後の落差、自分が作ったものじゃないような拒絶感に惹かれたのだと思います。
−「何を表現しているのか」と聞かれることの多い作品だと思うのですが、どのような思いで作品を制作されているのか、お話をお願いします。
卒業後の転居が、客観的に自分の制作を見つめ直すきっかけになり、ぐちゃぐちゃに作るままではなく、自分が土と関わると何が出来るのかということを冷静に考えるようになりました。ものを作るモヤモヤするエネルギーみたいなものが、周りに散らばっていたのを、自分の方にベクトルを向けられた、というようなイメージです。土を触ると勝手に出てくると思っていた、知らない自分と呼んでいるものの正体が曖昧だったり、それ自体が歴史や社会、時代といったものと接点があることに気づかされました。現在は、自分が作りたいものを作るというよりは、素材の条件に左右されながらも出来る自然な形を意識し、規則的に棘を作り、積み上げていくということをしています。
−行為自体に意味がある、という部分が強いのかなと思いますが。
自分の「こういうものを作りたい」という思いには、これまで生きてきた垢みたいなものがたくさん詰まってて、そういうものを遠ざけるために、あえて秩序が生まれる行為を選んでいます。なるべく純粋に形を作ることで生まれる、必然性を含んだ形に美しさを感じます。結晶が生成されるように、自然に生まれるものを目指して形が出来ていく、というのが理想です。
−望月さんは作品についてお話しされる中で「生き物」という言葉を使われてることもありますよね。そういった観点についてはいかがでしょうか。
細い棘を作ってくっつけたものを焼くのですが、窯の中での土が一番生き生きしているなと感じています。土は温度を上げるほど一旦柔らかくなって、そこで棘が曲がったり粒同士が動いたりして、冷めるとピタッとその形で固まって、窯から出てくる。そういったところに面白さを感じています。生きているものを、いかにも生きているように見える有機的な形で作るのではなくて、かつて生きていたものが、生きた証として窯から出てくるというようなイメージです。妊娠・出産を経験した際、赤ちゃんってどこからが生まれていることになるのだろうか、お腹にいる間は生まれていないけど確かにここにいる、といったことを考えることがあって。窯で焼く前の土は、そこに存在はしているけど、生きた証として残ることはできなくて、焼成の力を借りて、はじめて生まれ出てくるように感じるんです。それは生きて出てきた形、生きた証だと思っています。私は、形がないと生きたことにはならないと思っています。だから生きた証というのは尊いもので、命を宿すということは、個体の意思を残せること。残せるから次の世代に伝わることができる。バラバラに生きている個体同士だけど、永遠につながっていくことが出来て、これまでのつながりがあったから自分も存在している。そういう気づきがあるのが、自分にとっての焼き物なのだと思います。
−陶芸家は焼かないと作品ができないので、焼くことが重要な要素ではありますが、その中でも望月さんらしい焼成感を持って制作されていることが伺えます。今のお話を聞いてもう少し詳しく聞きたい点、ご質問などをお願いします。
(質問1)集合している作品は一つ一つで作品が成り立っているのか、この展示の形で一つの作品なのか聞かせてください。
いつもは奥にある作品のように一個を一つの作品として表現していますが、今回の床置きの物はとりあえず大きく広げたいと思って。たくさん作って、作った後に波みたいだなとイメージして、タイトルも「Waves」としました。いわゆる海の波ではなくて波長とか、見た人それぞれの色々な捉え方があると思います。
(質問2)窯の捉え方がすごく神秘的で、おもしろいなと思いました。窯で焼くことについて、自分はそういう風に感じたり考えたことがなかったので、すごく興味が沸きました。焼くことで作品が一番生き生きとしているというお話でしたが、窯の中での生き生きとした姿をどのように想像されているのか。作品を作っている時と窯の中での様子とがどう結びついていているのか、作る時と焼く時のイメージの関連性をどう想像しているのか聞かせてください。
トゲトゲの作品は8年くらい作っているのですが、最初はもう少し棘が丸っこくて、気づいたら今のように細くなっていました。作った自分にしかわからないけど、焼いた後、すごく動いたなと思うんです。棚板の上にシャモットとという粉を引いて、作品を縮みやすくして焼いているのですが、そこに本焼きする前の作品のボコボコの跡が残っていて。その跡と本体を見比べると、完全に動いた跡がはっきりとわかるので、そのことを踏まえて作るうちに棘が細くなっていった形です。自分ではあまり意識していなかったけど、どんどん変形してどんどん棘が細くなっているなと感じています。

−まずはなにをきっかけに陶芸を始められたのか教えてください。
僕は沖縄の生まれで、陶芸がやりたくて沖縄芸術大学に進学しました。描いている意匠も、沖縄の植物がモチーフになっています。元々は職人的な仕事に憧れがあったのですが、大学進学後は陶芸の世界にどっぷりと浸かって。古いものを見るのが好きで、そういうものを見ていくことと、元々自分の中にあったものを感じ取っていくことを重ねて、自分の工芸感が形成されたと思います。いま制作に使っている磁器土は、完全に乾いてからでも加工ができる素材です。土が水分を含んで作りやすい状態から、どんどん積み上げていって、焼成する。制作していく工程において、そういう「積み上げていく」ような感覚が、僕の中の工芸感にあります。
−屋我さんはすごく勉強熱心な方ですよね。色々な作品も見てらっしゃいますし、陶芸家の考え方も学ばれていて、お話を伺ったときにも様々な陶芸家の名前が出てきたのが印象的でした。そういった過去の作家、作品とご自分をどう繋げて考えているのでしょうか。古代から現代までの流れの中で自分をどう捉えているかという、今回の展示の大きなテーマでもあるのですが、そういった点について聞かせてください。
陶芸というものが生まれて、作家と呼ばれる存在が日本で定着してきた時代、大正から昭和くらいですね。その時代の人たちが憧れてた焼き物って、古陶なんですよね。いわゆる中国の焼き物だとか、日本の桃山時代くらいまでのもの。そういったものに憧れて、それをどうにか自分に還元して、ものを生み出してきた人たちに僕は憧れています。僕は伝統工芸の世界でコンペなどにも出品するのですが、そういったところに出品する人たちもやはり、伝統を継承した上で自分でまた生み出してく、という感覚があって。そういう世界で制作をしていて、僕もやっぱり古いものが好きなんですよね。僕が今使っている技法は、僕が創り出したわけじゃない。自分の中で表現したいものと、その技法をうまくリンクさせて作り出している、というのが今やっている仕事です。
−一般的に青白磁というと、涼やかで冷たいイメージがあるかと思うのですが、屋我さんの場合はそういった印象とは違うニュアンスで表現をされているとお聞きしました。
青白磁は、スカッとした涼しげなイメージが一般的にありますし、僕自身もそう思っています。僕の場合は、影青という(掘りを入れた生地に釉薬をかけ、厚く溜まった所と溜まってない所とで陰影を作り出す)技法を使って表現しているのですが、その釉薬の中に、温さみたいなものを入れ込みたいなと。地元である沖縄の温かみや湿度、山でも海が近くて潮風が当たっている感覚とか、そういう空気感をなんとなく感じてもらえたらと思い表現しています。近づいて見ていただくとわかるのですが、僕の釉薬は柚子肌といって、柚子の皮のように表面がボコボコとなっているんです。そういうものが入ることで、青白磁の中に湿度的な、温さみたいなものを感じることが出来るのではないかと思っています。沖縄のモチーフを表現するための、テクニック的な部分の話ですね。
−近づいて見て頂くと表面がボコボコとなっている部分が見えるかと思います。そこに光が当たり乱反射してノイズが生まれる。直接光が反射するよりも柔らかい光の見え方になると思うのですが、そういった点において、技術を用いて表現に変えているところが屋我さんのアプローチの仕方ですね。今回は日本家屋の中、自然光で見て頂く展示となりましたが、屋我さんはこの空間に、作品をどう置くかというところから考えて制作をしていただきました。光の見え方やこの空間で表現したかったことなどを、もう少し詳しくお願いします。
恩師からの受け売りと、僕の持論が合わさった考え方でお話させていただきます。最近の陶芸の作品はマット調とか、ちょっとシックな印象の作品、表面がつるっとしない、ぴかっとしない様な作品が多いなと感じています。それは、いまの僕たちが生活してる光量が、昔と変わってきたというところに関係していると思うんです。いまの時代の家の中に、僕みたいな作家の磁器作品を置くと、ぴかっと光りすぎてしまう。だからサンドブラストを当てたりして、光をあまり反射しない様に作った作品が多いなと、ちょっとした偏見かもしれないけど、そう感じています。この家(海老名三平宅)で生活していたら、昼間でもこういう暗さの中で過ごすということですよね。こういう建物でいわゆる昔のぴかっとした白磁の壺をぽんと置くと、すごくきれいなんです。そういう美的感覚について、今の世で人はどこまで探れるか、その機会がどこまで持てるかという思いが自分の中にあります。そんな中、自分の作品を日本家屋で展示する機会をいただいけたので、感謝して制作していました。
−ありがとうございます。いまの暮らしの中での光が昔とは違うというのはおもしろいなと。そのなかでどう表現するのかを意識され、今回のシチュエーションの中でこういった作品を展示していただいたということ、興味深くお話を伺うことができました。今のお話を聞いて、もう少し聞いてみたいことなどありましたらご質問お願いします。
(質問)以前初めてご挨拶させていただいた時は、作品を拝見していなくて。今回チラシで作品を初めて拝見して、作品とご本人が結びつかなかったのですが、お話を聞いていると屋我さんの感覚はとても日本らしい捉え方だと感じられました。ご自身の来歴である沖縄と表現を結びつけているというお話から、作品と屋我さんとのつながりがとてもクリアになって、いろんなことが腑に落ちながら話を聞いていました。屋我さんの作品に限らずかもしれませんが、伝統工芸といわれる展示でよく拝見するスケール感について、前々から気になっていることがあります。生活者の視点で見てしまうと、壺や皿というすごく日常的なモチーフを使いながら、今の僕らの生活と乖離しているスケール感の物が多いなと感じていて。今回の屋我さんの作品もすごく大きなお皿なのですが、スケール感が伝統工芸の中でどういう重要性があって、どういう捉え方をされているのかお聞きしたいです。
サイズ感については僕も疑問に思うことは多々あります。ただ技術や技法の伝承の中で、置いて飾る作品としての限界値があり、コンペで競うことを目的にそういったサイズ感で作られているのだと思います。弓場先生*という研究者の方がおっしゃっていたのですが、日本の陶器は使う。それに対して中国陶器は飾る、韓国陶器は遊ぶ、と。これはまさにそうだと思っていて、(使うための器として)高台などは西洋には無い日本ならではの文化だなと思います。そういった、使う範疇のギリギリのサイズ感でみんな競っている気がします。大きい作品は圧倒されるし、説得力もある。大きいものをまとめるのには力が必要ですが、小さいものは凝縮されて良いものに見えがちなイメージがあります。例えば、ここに落ちているドングリを大きくしたらどうなるか。ただ大きくするだけでは、何かすごくでっかいものがあるなというくらいの印象になってしまうと思うんです。「あっ、かわいい」という印象がギュっと詰まったドングリの良さ、それが表現されない。技術と使うものの限界値のバランスを探っているようなイメージです。本当はもっと大きくしたい、そうしたら圧倒されるものにすることができる。でも、それだと使うことができなくなる。そういった感覚が僕の中にはあります。
伝統工芸の世界でも、全体的にスケールアップしていった時代があり、その後だんだん縮小して、また大きくなってと、そういった繰り返しもあるみたいです。最近は、割とスケールダウンしてきている気がします。近年は情報の伝達が早いこともあってか、伝統工芸を見ていても5年前と明らかに雰囲気が変わっていて。おそらく今までだと10年や20年で変化していたスパンが、5年、3年と縮まっていくかもしれなくて、本当に早い。すぐ飽きられてしまうというか、同じものだと思われてしまうので、新しいものがどんどん出てきているような空気を感じます。そういった流れの中で、スケールダウンしてきているような印象です。僕には韓国人の先輩がいるのですが、体格的にリーチが長くて、とても大きな壺を作るんです。すごいなと思っていたんですが、本人は「自分のリーチなら、本当はもっと大きものを作れる」と言うんです。コンペに出品した時に、色々な先生たちから言われたから、今のサイズ感にしていると聞きました。「だから屋我ぐらいの体型でも全然これくらいの大きさのものは作れるよ」と言われて、改めて伝統工芸の世界では、コンペというものありきのサイズ感なんだと認識しています。
*兵庫陶芸美術館 弓場紀知副館長
−ありがとうございます。最近伝統工芸の展示を見たときに小さい作品もあるなと感じたのは、そういうことだったんですね。
スケールダウンしているはこの2年くらいですね。また大きくなったりするかもしれないですが。

−横田さんは、元々は神奈川の方で生まれ育って、お仕事の関係で今は豊田市に移り住まれて制作をされています。焼き物といえば器というイメージがあると思いますが、そういった常識的な考えを壊すような、ダイナミックな制作をされている作家さんです。そんな横田さんですが、まずはなぜ焼き物を始めたのか、というところからお話いただけますか。
大学へ進学するときに、まずは普通科への進学を考えていたのですが、勉強が苦手だったこともあり、美術大学への進学を選びました。美術大学の中でもデザイン科、日本画科、工芸科など様々な科があるのですが、形を作るのが好きだということと、色を組み合わせることが好きだったので、当初はガラスがやりたくて、工芸科へ入学をしました。私の通っていた女子美術大学では、陶芸、ガラス、染め物、織り物の4つのコースがあり、1年生の時に全てのコースを体験します。その中で、ガラスも楽しかったのですが、磨きの技法において自分の性格に向いていないと感じる部分がありました。一方で陶芸は、粘土を触った時に自分の中でしっくりきたというのと、自由に形が動いていき、変えられるというところに土の面白さを感じて、陶芸を選択したというのが、一番最初のきっかけになります。
−土ならではの表現に魅力を感じたというお話ですが、初めの頃と現在とで土に対しての意識が変わってきている部分もあるかと思います。今回の作品の「ツチ・ビト」というタイトルにも関わってくると思うのですが、そのあたりについてはいかがでしょうか。
最初の頃は、自分の作りたい形を目指して、粘土に対してアプローチをしていました。しかし焼き物はその性質上、思い描いたイメージを実現することが困難で、粘土を積んでいく段階でゆがみが出てしまったり、焼きの段階でヒビが入ってしまったりなど出来上がりが納得のいかないものになる経験が重なっていきました。そんな中である時、そもそも焼き物において、自分の思い描いたものを100%表現しようと思うことが間違いなのではないかと考え、逆に自分の「こうしたい」を一切なくして粘土と関わるということをしてみよう、と思ったのが、今の作風に変わった転機だったと思います。土と人間、つまり制作者である自分が関わった時にどんな形が生まれるんだろうか。土だけでも作れないし、土がなければ作れない。土のゆがみやヒビ割れなどを受け入れつつ、自分がその中でどう成形していくのかということに、現在は主眼を置いて制作を進めています。
−作り方自体も独特な部分がありますよね。
土は私にとっては扱いやすく、比較的思い通りの形になっていく素材なのですが、それだと自分のイメージを押し付けてしまうことになり、土で制作する意味から離れてしまいます。なので現在の制作では、例えばひたすら真っ直ぐに円柱を積んでいくと、ある程度のところで土が自重に耐えられなくなって崩れ出すのですが、その崩れた形を自分が受け止めて、成立させるというような過程で作品を作っています。制作をはじめる時は、高く積んでみよう、下の方を丸くしてみよう、程度のイメージしか持っていません。先を尖らせたりとか、二つを繋いでみたりとか、そういう最終的な形状は作りながら決めています。
−自然に対して思い入れがあると伺ったのですが、そのあたりについて制作への影響はありますか?
自然の持つ、人間が作り出せない力強さや、長い間ずっとここにあったという歴史に魅力を感じていて、土もその一つだと思っています。ものはものだけでとても存在感があって魅力的だと思います。だから、そこに自分がどう関わったらそれ以上のものができるのだろうかと考えます。その中で自分がどう関わるかを考えながら制作するため、自然の力強さというのは常に頭の中に置いています。
−土を使って大きな作品を作るのは、単純な大変さもあると思うのですが作品のスケール感についてはどのように捉えていますか?
昔から何故か大きなもの、自分が圧倒されるもの、包み込まれるようなものが漠然と好きでした。今の作風で作品を作っていると、自分が思っていない形に土が動いたりすることに、圧倒されることもあります。実物としての大きさももちろんありますし、もの自体は大きくなくても力強さという意味でのスケール感は意識して制作をしています。
−今のお話を聞いて、ご質問などあればよろしくお願いします。
(質問1)実際に作品を拝見して、チラシに載っていた作品があんなに大きいとは思わなかったので驚きました。お話を聞いた上で見ると、スケール感や圧倒される感じがさらに面白く感じられました。単純な質問なのですが、この大きな作品をどうやって焼いているのですか?
ここまで大きな窯はなかなか無いので、一つの作品として成形した後、一番粘土が強いと言われている、焼く前の生乾きの状態のところで鋸などで切断します。それを部分的に焼き、焼成後に合体させて一つに戻しているというような工程を踏んで制作しています。焼き物としては邪道だと思うのですが、スケール感を考えて、そのような制作工程を取っています。
(質問2)作品の形が生き物のような印象を受けたのですが、そういったことは意識していますか?
タイトルに「ヒト」とついていることもあり、「ヒトみたい」「生き物みたい」という感想はよくいただきます。自分自身は制作の時にそういうことは意識せず、自然にできる形で作品を作っています。土が動いた中で生き物らしさが出ているのかなとも思えるので、そういった言葉は非常に嬉しく受け止めています。

アーティストトーク
9月19日(土)13:30-15:00
会場:田舎家(青隹居)
申し込み不要・参加費無料
| 会場 | 豊田市民芸の森 (愛知県豊田市平戸橋町石平60-1) |
|---|---|
| 会期 | 2020年9月19日(土)〜10月11日(日) |
| 開館時間/休館日 | 9:00〜17:00 入館は16:30まで ※平日13:00以降および休日にはガイドによる案内あり |
| 入場料 | 無料 |
| 主催 | 豊田市民芸の森 |
| 監修 | SHIMAYAGI ART |
| お問合せ | 豊田市民芸の森 0565-46-0001 |


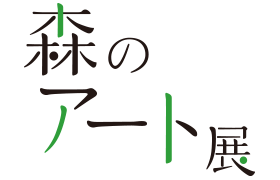
豊田市に生まれ、民藝の普及や猿投古窯の研究に尽力し、同時代の芸術家の支援も行った日本の実業家本田静雄氏。 その研究室および邸宅の跡である「豊田市 民芸の森」にて、 豊田市にゆかりのある作家や、民芸と関わりのある作り手などを紹介する企画として2017年から始まりました。
愛知県豊田市平戸橋町石平60-1
TEL.0565-46-0001
民芸の森 公式HPへ